★この動画は2020年3月28日に配信された放送です★
↓元動画↓
※当チャンネルは岡田斗司夫さんの動画管理元であるガジェット通信様と
正式な契約の元でMCNに加入しております。
↓岡田斗司夫さんのチャンネル↓
https://www.youtube.com/c/toshiookada0701
===人気の再生リスト===
▼【警告】ヤヴァい研究結果が出てきています。1日6時間以上スマホを見ている人は要注意です▼
▼【岡田斗司夫】スマホは人間の能力を下げる▼
https://youtube.com/shorts/ma8g4pdyUIE
▼【岡田斗司夫】スマホ依存の恐ろしさ▼
https://youtube.com/shorts/Uth5fRLRHMM
#としおを追う #岡田斗司夫 #切り抜き #切り取り
#サイコパスおじさん #ジブリ
★【岡田斗司夫公式】Twitter
Tweets by ToshioOkada
★【岡田斗司夫公式】Facebook
https://ja-jp.facebook.com/frex.otaking/
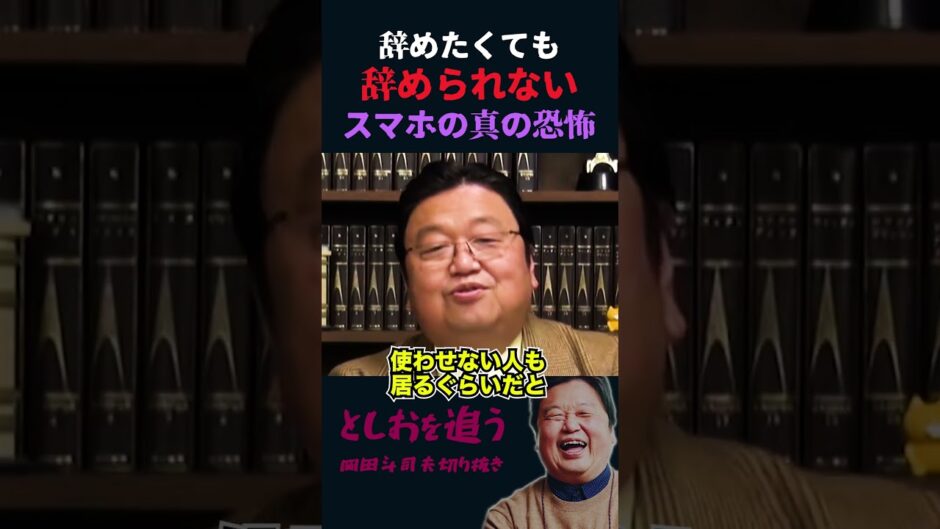
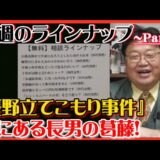

依存性があるって、解るなぁー
休みの日は4 時間以上ユーチューブ見てる 永遠に暇潰せる。
↓本編↓
https://youtu.be/TLse-t-cbVI
確かにヤバい😅
スマホない頃の方がみんな生き生きしてた
スマホないと今の時代なんも出来んやんっていうこと自体が良くないのかもしれない
これを夜中1時に真っ暗な部屋で見てる俺
これを夜中1時に真っ暗な部屋で見てる俺
日本のガラケーはかなり先を行っていたので、20年以上前から日本人は耐性があります。
間違いない!
スプラとゼルダ楽しすぎてスマホ触る時間クッソ減ったで!ドラッグにはドラッグで対抗や!!
通学の高校生が多く乗る電車も、わりと静かです。皆スマホに必死で、雑談は先生の前とかでやってるようです。学校が通学時のスマホ使用を禁止しているのに、優等生ですら守ろうとできない。…そこに目をつけると、薬物というのも納得できます。
時間と集中を奪おうとしているという指摘には、
ヨーロッパ的知性を感じます。
もしもここに加えて、
AIによる文章作成能力についての考察があれば、
なぜスマホ中毒の人が鬱になるか、推察はできる。
深夜3時にこの動画見てる自分と重ねてすごく納得した
金があるか無いかが最大の原因だと思う💰
寝る前のスマホは光よりも操作のほうが寝付けなくなるらしいよ。
眠れない人はそこを意識すると昨日より眠りやすくなるかも
人は好奇心と生存本能の為に情報収集したい部分がある。
集団に溶け込もう、仲間を得よう、自分を認めてもらいたい気持ちがある。
これは種として生きる為に、より活きる為に渇望に近い部分なんだよね。
ある意味でスマホやタブレット、インターネットを持ち歩き常に身近に持ち歩く事は
物理的な移動効率の飛躍的な向上につながった自動車よりも
人間の種としての精神的な要素、生活に大きな影響を与えたのかもしれない。
今後は網膜ディスプレイやピアス型PC、埋め込み型PC、
ダーム(冷えピタのような)皮膚接点ポートなどが使われる世界になるのかな。
計算処理を脳に頼らず、個人の能力に作用されず出来るようになれば
人の社会での価値は芸術性や発想力の豊かさが重視されるようになるのかも。
高齢化による物忘れ、判断能力の低下などが
デバイスによってサポートされるようになるのは良い事ですね。
ほんとにそうだけど気持ちいいんだこれが
自分も周りもスマホ持ってない時の方が生きやすかった
スマホはドラッグ…言い得て妙です。海外の風刺画で鼻からストローでスマホを吸うのがありましたね。様々なアプリを入れたり、動画サイトでも自分の興味のあるものを視聴出来るのでドップリと浸れます。本当に恐ろしいです。
まあその通りなんだけど、IT化が進んだ昨今は無能な働き者が世に出るよりスマホで引きこもりにしていた方がいいと思う。
便利っちゃあ便利なんやけど暇があったらスマホいじっているもんな。
その動画をスマホで見てるって言うね
やばい……これが薬の気持ちよさか………薬物中毒者になんでこんなんで……って言えんな……………………気持ちいい………………………
ほんとにドラッグなんだろうなって。現にテスト期間入っても勉強全くしてない私がいる
睡眠障害の子供が多いですよね
昔と今の満足度は変わっていないし、むしろスマホでSNSで他人の生活を眺められる様になってから、差を感じて、嫉妬心やネガティブ意識が出てくるのかな?と思ったり
スマートなのは人間ではなく電話だもんね
実際、忙しくてあんまスマホとかSNSに触れられない時期はあんま評価とか気にしてなかったけど、自由な時間が増えてSNS触れる時間が増えるようになってから👍🏻やらリプライやらで嬉しい悲しいが上下するようになってらから、ほんとにやばいんだなって感じた